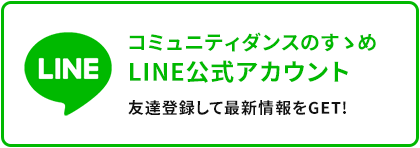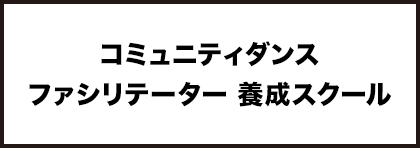マニシア インタビュー3部

2007年1月、福岡を拠点に全国で活躍中のマニシアさんに
JCDN佐東がインタビューをおこないました。
『マニシアさんのすべてがわかる』4部構成!!
+ + + + + + + + + +
第3部
―今、ワレワレワークスではどういうことをやっているんですか?
言葉にすれば『障がい者とプロダンサーのコラボレーション』なんですけど、学びあいっこ、探りあいっこというのがお互いにあり、でも健康な子どもたちも入ってくるわけですよ。アレルギーがあるから、何かいい空気のあるグループにみたいな。他ではなんか違う、みたいな。だから表現活動的なことになっていますね。最近はもっともっと幅広くなっているのかな。
最初は障がいのある子どもたちのもつ表現に触れることで、プロのダンサーが自分のフィールドに帰ったときにすごく伸びている、というのを見るのが私の楽しみで、そして彼らが感じてくれるっていう楽しみがそのプロジェクトの中心的な思いだったんですけど、そして作品を創る上で「何が出来る?」というのを問い続け、リズとの出会いで、彼女の創作法は」同じようであっても舞台が素晴らしくアートになっている。私たちの表現を本当のアートにするためにはもっと真剣に取り組まないといけない。ダンサーがダンサーでありながら人間であるという、それをアートにするには福祉じゃいけない、って感じて、すごい戦いですよね。それを仲間たちと共に学んでいくためには本当にもう舞台だけじゃなくって、皆でピクニックをするところから始まるというか。その気づきから、ある意味今はすごく良い核みたいなものができていますね。
―福祉じゃなくて芸術にもっていきたいと思ったのはどうして?
舞台を重ねているうちですけど、2006年からワレワレが出発して、1番始めはカズキくん(ジャッキー)との出会いから、ジャッキーの頭の中にレマンツァという国があるということで、「おもしろいね。でもそれは彼の空想だけど、現実とマッチしている部分がいっぱいあるし、現実をまっすぐ見るのではなく上から見るのでもなく、ナナメから彼らは見ているな」という感じで、それを舞台で表現してみようと創った作品が今もずっと続いているんです。だから素直に、こうじゃないといけないじゃなくて、作品と共に変化し続けるワレワレワークスというのがあっていいんじゃないかなって思いますね。
福祉っていうのは彼らに付き物なんです。やっぱり障がいがあると“福祉”っていうかなり枠があるんですよね。その枠のある人たちっていうと、関わっているスタッフも結構こうじゃないといけないっていうのを決めた日本の福祉業界っていうのがあるじゃないですか。それでヒロシとの出会いで『工房まる』っていう新しい福祉に出会い、『工房まる』は「そうじゃないといけない」っていう福祉を彼ら独自の表現っていうものアートとしていて、絵なんですけど。そういうダンスのグループでありたいなという目標があるわけですよ。そして同時に枠のある福祉に、ワレワレワークスに関わっているお母さんたちからの依頼でセラピーの実践のために行ったんですが「かなり固いなー」スタッフがと感じました。「こうじゃないといけない」がいっぱいあって。なんか全然、アート発表会とかいいながら彼らの自由な表現じゃないし、自由とかいいながら画用紙だけで描かせるし。でも私はそれをやりたいんじゃない、って感じて。ニューヨークにいた頃のダンスに燃える自分と組み合わせていく、みたいな目標が見えてきて。そうするとすべてをニューヨークレベルまでもっていこうとする自分がいるんですよね。

そして「踊りに行くぜ!」にヒロシとデュエットで出た時もすごい挑戦で、オーディションから、私たちでいいかなー、きっといいみたいな感じで、結局出演することになり、福岡で一番おしゃれなイムズで発表するわけじゃないですか。それには、この前の『47memories』の中で2回しか練習できなくて車椅子ダンスというのを出したのと同じくらいの練習量なんですよね。彼と練習していくうちに、練習場所もないし、私が抱えないといけないし、私がおむつがえもしないといけないし。じゃあ練習するって張り切ってもお風呂の時間があるから、2時間あるうちの本当に練習したのは30分かなーみたいな感じで、いっぱい私は汗をかいているけれど、踊りで汗をかいているわけではなくて。彼の介護で汗をかきながらイムズにも連れていくわけですよ。それでもう集中しない自分がいて、もう体力的にも落ちている自分がいて、でも踊りたい自分がいて。「踊りに行くぜ!」という言わば私たちの“芸術”のステージという目標そのものでした。まず自分を出せ!みたいな気持ちが本番前にあって、もとの感覚を取り戻し、ヒロシとも上手くいき、たくさんの拍手をもらいました。
そして次にグループとしてプロレベルで舞台に出していくというのがずーっと目標で。セシリアと一緒で助成金に頼らずにグループを継続させてということで、自分のモダンバレエというものを活かしたクラスの子どもたちというのが割といっぱい生徒としているので、彼女たちとワレワレワークスをコラボレーションしていけば、舞台が成り立っていけるわけですよ。「満席に近い状態」というのが目標でありたいので、私の中では。そこはプロ意識ですよね。だからそこの中で2006年からずっとやっているんだけれども、ワレワレワークスだけで作品発表やっていけたらな、というのは目標にはありますね。多分日本の文化の中では、まだまだ時間はかかるかなーって思いますけど。でも福岡の中で劇団っていっぱいあるじゃないですか。彼らはどうにかやっていっているようだし。じゃあダンスじゃなんでやっていけないの?って思うから、そこはやっぱり目標は、実践していっている人たちがいると思うだけで可能性は与えてくれていますよね。若い人たちはすごいですね。
―『47memories』での、パパダンスはどうして始めたの?
パパダンスの一番最初のきっかけというのは、ニュースとか新聞とか見ない自分に、公園で殺された子どもというニュースが日頃ニュースを見ない私に情報として入ってくるわけですよ。自分って結構必要なものしか入ってこないっていう信念があって、なんか「公園で殺された子ども」っていうのに、ふって耳を傾けて。なんで私はこれを聞いたんだろうって思って、この事件知りたいと思うと、実は母親が殺しているわけですよ。するとこの社会ってなんだろう、何が問題なんだろうって思い「あーコミュニケーショなのかもな」って。
それで「コミュニケーションの問題ってなんだろう」「あ、父親が話していない」というところにいきついてくるんですよ。それで父親が働いて働いて帰ってきて、単身赴任で、実家に帰ってきて、週に1回帰ってきて「お父さんくさーい」とか言われている。これってちょっと違うよね?って。自分の父親とはすっごくいい具合で結ばれてきたよねーみたいな、まあ自分の父親は今もう認知症でかすかに私のことを覚えてくれてるのみ、みたいな。すごく良い親子関係が昔はあったわけですよ。現代病みたいな、子どもたちは健康だけれども、精神的にやられてるみたいなケースがいっぱいあるんですよ。これを回復していくには、まあ“人間回復運動”ですよね、なんだろうと思うと、「あーお父さん踊らせれば」と思う、面白い自分がいるわけです。それで自分もワクワクするし。つながりのある5・6年生で子どもは成長の段階で心が変化するなーと思ったので、1人活発なお父さんがいたし・・・あ、そのお父さんはリズのいるワシントンDCについてきたんですよ。子どもと離れられないからって。その時の美術館での発表で、お父さん自身ダンスデビューしているんです。
その彼に自分の気持ちを伝えたんですね、その殺害にあった子どものことを含めて。そしたら「まあ実験であるんだったら、やってみようかな」って言って集めてくれたんです。そしたらすっごいなんか良いWSになって、目をつむって自分のお父さんの手を当てるゲームでお父さんがもう涙を流す、みたいシーンありありなの。そして「これを広げたい」という思いがあったんだけど、その年代だとやっぱり部活とか、もう6年生だったのでもう中学生に入る準備時期だったり。続けて、そして広めていくには親父の会へのアプローチも企みましたが、子どもが自立し出し、部活についていくだけのお父さんがたくさんで、それで絆を保つみたいな。親父の会のお父さんたちは何なりと関係を持とうとしているからいいんですね。
敢えて挑戦しようと別の種類のお父さんたちを集めようともしたんだけれど、流れがなく壁にぶち当たった気がした頃に、九大のパネルディスカッション“感性とは”へのパネラーのお誘いがあっんです。読売新聞の人が私の言葉の「直感にしたがって活動する」という言葉にすごく感動してくれて、それで取材をしたいということで色んなWSやってるけれども面白いWSないかな、と尋ねられ「そういえばパパを対象にしたWSって面白かったですよ」って。そしたら「それやってくれませんか?」ということで、突然だったので公募でなくバレエ教室の方々に『パパ集まりませんか?』みたいなメールを出して、結構集まってくれたんですよね。それで集まってくれたパパたちの2人が、新聞にも大きく出たせいもありダンスにもすごく感動してくれて。それで「これWSだけじゃなくて作品にもしたいな」と思い始めて、なんかグループ創るべきかなと思ったら、すぐその2人のパパたちが他のパパたちを誘ってくれて。そして作品づくり開始というわけです。あの時が6組来てくれてあとの2組は見学に来たんですけど、「子どもがやるっていうから」と、すぐその2組のお父さんたちも踊り始めましたね。後で、辞めようかと思ったこともあるけど子どもがやるっていうから続いたっていう話も聞きましたね。

一番最初は10月だったんですけど、自分の公演で踊ってもらいました。控え室でドキドキしているわけですよ、初めての舞台ですし。もうすごい硬直した顔を見て、そして舞台で1作品終えて帰ってくるとワーッて浄化されているパパたちがいるんです。「やっぱり舞台には力がある」って。まあその前から、次のカンファレンスがイタリアなので『即興とか舞台には力がある』っていうので小論文を書いたんですけど、その彼らの顔を見て「やっぱりそうだ!舞台のはちからがある」って実感しましたね。とにかく何かあるって思いますね。“ダンス”っていうのと“舞台”っていうのをもっと今後つきつめていきたいんですけどね。
そしてパパダンスというのを本当は人間回復運動でやりたい、広げたいという自分の気持ちを捨てなくてもいいけれどもそんなに大々的でなくても、小グループでも、笑顔をつくっていくことで、「この指とまれ」でとまった人数がパーフェクトで、その時の自分にとってパーフェクトな人数・サイズなんだなと思い、それに自分にOK出せることが次に向かえる自分をつくると思いました。
だから気持ちも色々編みこまれていって、楽しくて仕方ないです、今は。以前はダンスをつくろうとか、こうしたいという時点の自分だけで、苦しかったんですよね。もう途切れてしまってました。かくかくしたがたくさんあったし、今は本当にもう続いていくし、この先どうなるんだろうというワクワクがいっぱいあるし「来る人が来る」というなんかゆとりがあるというか。年の功もあるんですかね。
To be continue……
最新記事 by NPO法人JCDN (全て見る)
2014年5月15日